> げんちゃんが、自我の固まりのように見えるこの頃ですが、前回のブログで、ギャングエイジと教えていただきました。検索してみると8歳から10歳と書いてあったので、今1年くらかしら、と思っていたげんちゃんは、もっと先に行ってるのかも・・・(変なとこで喜んだりして)
でも、昨日久しぶりに学校見学をしました。げんちゃんは、普通クラスで音楽のコーラス練習をするところでした。近々ある音楽発表会に学年全体で出るらしく、課題曲を3クラス集まって練習してました。実はげんちゃん、このコーラスの時間が、とてもいやみたいで、前日から、
「音楽なんてなければいいのに、あ~いやだ!」
と言ってたました。
のっけから、げんちゃんは、列に入ると、いやそうな顔で、隣の子に何か話しかけてます。音楽が始まると、下に落とした楽譜を、足で、ちょいとけったりもしてます。音量がマックスになると、耳をふさいで体中で抗議してるみたいです。私が見学に来てるので、先生は、げんちゃんの横に行って、楽譜を見せながら気分をもりたてますが、げんちゃんはかわりません。
最初から最後までそんな感じでした。途中、私が廊下に呼んで、
「ここ歌ってごらんよ。げんちゃん、ピアノしてるから、楽譜見たら少しは歌えるよ。」
なんて、教育的指導に交えて言ってみましたが、効果は、当然のごとくありません。
音楽が終わってから、支援クラスに移動しました。支援のH先生とクラス担任のT先生を交えて、私が、先頭に立ってお話ししました。
「げんちゃん。ちゃんとしないと、だめよ。歌うのいやなら、参加するのやめる?参加したいのなら、ちゃんとやって。でも、いやだったら、参加しなくてもいいよ。どうする?」
と私は、静かにげんちゃんに聞きました。耳をふさぐのが、感覚過敏によるものかも、ちょっと聞いてみましたが、そうでもなさそうでした。
げんちゃんは、やりたくないと言っていたので、当然、参加しない、と言うと思っていたのですが、
「いやだ。出る。」
と言います。え? 何せ、去年は、教室にいたくない時は、さっさと保健室逃亡をして、さんざんみんなを困らせたげんちゃんです。やりたくない授業でも、出て参加する、という意識が芽生えているのでしょうか。ちょっと意外です。
「ちゃんとできる?」
うなづくげんちゃん。私は耳をおさえるポーズで、
「ねえ、げんちゃん、こうやって、お歌歌わないのって、とても感じ悪いよ。もし、げんちゃんが、お話ししたりするとき、相手がそうしたら、どうかな?」
「いやだ! 」
まあ、こんな風です。
去年と違うげんちゃんは、目の前のおもしろくない忍耐の時間に対して、抵抗するものの、それは、クラスの行事で参加しなければいけないことは理解しています。ただ、忍耐の仕方、対処法に限界があるということなのでしょう。
実際、コーラスの歌は、とても退屈な旋律でした。よく、他の3年生の子たちは、静かに、授業の趣旨に従って参加できてるな~と感心してしまいます。げんちゃんは、ホームスクールで参加できない時も多かったので、歌も覚えてないし、この授業がとてもいやだというのは、私もよく理解できました。
定形の子で、げんちゃんと同じように感じてる子がいたとしたら、その子は、忍耐して、とりあえず、参加することによって、時間をまぎらすか、時々よそ見をしたり、まあ、ちょっと注意されるくらいのことですんでいるのだと思います。それは、今、何をしなければいけないか、という目的意識と、育ってきている社会性による成果だと思います。
でも、げんちゃんだって、随分がんばってると言っていいでしょう。めだつ耳ふさぎという行為や、譜面を軽く蹴飛ばして床に放置する、という行為は、げんちゃんのオープンな性格にも裏付けされてるように思います。彼は、こもってないので、表現がストレートです。
現状にたいする適応としては、これが、せいいっぱいなのでしょう。でも、結果的に最後まで、教室におとなしく座っていたのです。
以前の抵抗スタイル(たとえば逃亡や、妨害行動)はげんちゃんの異常性を示していましたが、今回は、見方によると、ただの、お行儀の悪い子・・・かなり大目に見れば、そういう風にとれないこともありません。この違いは、私だけが感じるものかもしれないけど、大きな違いなのです。
帰ってから、すぐさま、連絡帳に書きました。
彼なりに相当伸びていること、そして、今、コーラスの時間を忍耐させたり、退屈な譜面を歌えるようすることは、時間的に、余裕のないげんちゃんにはオミットしてもいいのではないか、ということ。かわりに、今してもらいたいことをさせるのが、よいのではないか、ということ。
(もちろん、文面には、失礼なことは書きませんが、私の中でまとめるとそうなります。)コーラスの課題が終わるまで、今、げんちゃんが取り組んでいる、20までの加減計算より、ちょっと難しい計算のマス計算を、支援でさせてほしい旨を書きました。私がそのプリントを用意します。
やっと、20までの計算が何とかなった今は、そこから、少しでも、先につながる計算力をつけること、それが、今の最優先課題としているのです。しかも、11月に向けて、3曲をひくピアノの発表会もあります。
さて、有意義だった、普通クラスの見学を終えると、支援でのプログラム見学です。来週の親子レクリエーションでやる、お菓子作りの計画を皆で立てるということで、3つの支援クラス合同で、話し合いをするというものでした。担当の仕事を確認し、みんなで目当てを考えましょう。というものでした。げんちゃんは、
「てきぱきやる」
とさっさと目標を紙に書き黒板にはりました。支援クラスでは、他の子がのんびりしてる分、げんちゃんは、てきぱき、のびのびと、どんどん仕事をこなしていく感じです。
昼休みは、支援クラスで、給食もご馳走になりました。アットホームな雰囲気で楽しかったですが、そこにいる子ども達の、食べる口が、閉じれないのが気になって、咬むトレーニングをさせてみました。やはり、発音がだめな子は、口を閉じて食べることができません。
先生方と話は、粗大運動と微細運動の話しになり、発音は、微細運動の最たる物で、上半身がだめで、口を閉じて食べれなければ、やはりまだまだだ、発音までいかないですね。というようなことを話しました。先生方は、いつも、好意的に接して下さるので、つい、母というより、その日ボランティアに入ったママといった感じです。とても、よい先生方です。
ほんとに、支援クラスは、ゆるいです。一人一人、どこが問題点で、今、どういうステージにいて、どこからアプローチして、そのためにどういうプログラムを計画するか・・・・そういう、あたりまえとも言える、現状分析、目標設定、そのための戦略・・・・小さな目標と大きな目標・・・・そういう流れがないことがとても気になります。そもそも、そういうことを、個々の先生個人に丸投げしていることが、日本の遅れているところでしょうね。
だから、発達障害児をかかえた親御さんは、しっかり家庭でそのあたりを補う必要があるし、学校に、そのあたりのプラン提供も可能な限りしていく方がいいように思います。そのためには、出来る限り、学校にも通って、先生方とも親しくなっていくのがいいのかもしれないですね。
支援の子たちは、今のうちに、ここを伸ばすべきなのに・・・・口惜しくなる子ども達であふれてます。言うなれば、日本のシステムの不備とでも言うべきでしょうか。
いつか、私の今までのノウハウを、勉強会など開いてもらって、みなさんにシェアしていただく機会を作りたいな、という思いがよぎりました。とにかく、こうしたい、とまずは、思うこと。チャンスがあれば、踏み出すこと。そういう小さな歩みが、大きなことにも通じていくのかもしれません。
げんちゃんは、本番の親子レクレーションで、妖怪ウオッチを踊ると手挙げしたらしく、プログラムに入ってました。え~?大丈夫?と心配になって、帰りに妖怪ウオッチのダンスDVDを買いました。家でやらせると、ちゃんと歌って踊りました。へ~・・・やるね~。歌えるじゃん。(下手だけど・・・)
しかし、笑いますね~。コーラスはいやなくせに。まあ、確かに妖怪ウオッチの方が楽しいわな~。
自分のやりたいことをやりたいと主張し、やりたくないことはやりたくないと主張する。
やっぱり君は、進化してるようですね。
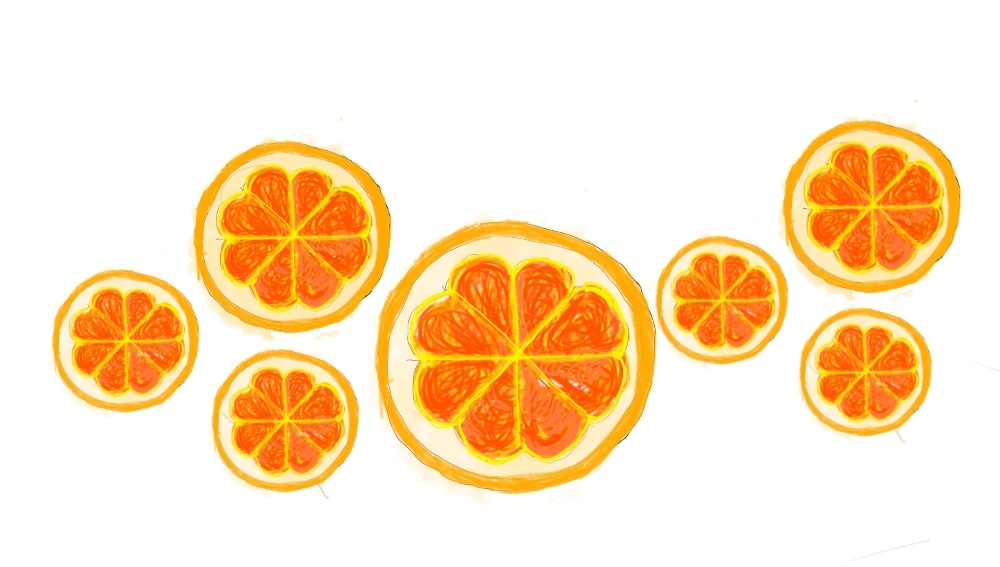
公開コメント 承認後公開
げんちゃんは、出たいんですね。
出たいのに、練習はちゃんとやらない。
普通に考えると、出たいならちゃんと練習しなきゃとなるところ、げんちゃん、結びついてない(理解できてない)可能性があります。
ということは、関連づけてあげたほうがいいと思います。
この場合、まず、出たい(肯定)と思っている前提で話したほうがいいです。
声かけとしては、
「げんちゃんは、コーラスでたい?」
と聞き、
「出たい」
と言ったら、
「ピアノも発表会でかっこよく弾けるよう練習するでしょう?コーラスも上手く歌えるように練習が必要なんだよ。頑張れるかな?」
と聞いてあげ、
「うん、がんばる」
と言ったら、
「すごーい、げんちゃん、頑張って。ママ応援するね。げんちゃん、お歌上手だもんね。コーラスの日、見に行くの楽しみだなぁ。家でも練習しよっか?」
と褒めてあげて下さい。
そして家でも、コーラスの練習がんばってる?とかママ楽しみだなぁとかたまにいってあげて下さい。
もし、上記の問いの時「出たくない」と言った場合、「ママ、げんちゃんのコーラス楽しみにしているんだけどな。」とか言って、反応をみてあげて下さい。
そして、だめよとかやめてとかの否定後は極力使わないほうがいいですよ。
あれ?ちゃんと読んでいなかったんですが、げんちゃんが音楽発表会に出たいと意思を聞いたのに、参加させないんですか?
その対応は、よくないと思います。
せっかく出たいと言ったんですから、本人の気持ちを尊重し、出させてあげて下さい。
本当に理解してなかっただけの可能性もあるし、母としては、応援、サポートしてあげて下さい。
げんちゃん頑張ってますね。ママも最初にげんちゃんに気持ちを聞いてから答えてる所、私も気をつけてる部分です。こういう子はどうしても上から押さえつけてる様な怒り方したくなりますよね。音楽、うちも同じです。うちは聴覚が過敏なので無理強いはできず、参加できたらすごい、のレベルですが。けど、耳を塞いで拒否をしてる息子を見るのは結構しんどいです。げんちゃんは、過敏とは違うけど、自分なりに逃げないで参加する、と発言。そこが偉いな、と思います。
ママにしか分からない事、特にこういう子はありますよね。同じ発達障害児でも全然一人一人違う。だからこそお母さんが、もしくはお父さんがしっかり成長を見逃さないようにしてあげないと。
ぜひ、意見をシェアできる会があれば、と思います。私は東北地方ですが、げんちゃんママ、junママさんはどうですか?
もし遠くても、いつかお会いする機会があればぜひに、と思います。
そして、ペアトレですが、私は療育訓練センターで受けました。ペアトレは元々はアメリカでADHDの児童の親を対象にしたトレーニングらしいです。望ましい行動、望ましくない行動に対する対処を学ぶもので、トレーニングそのものは至ってシンプルです。特別な訓練では無く子供全てに良い関わり方だけど、定型の子はそんなに気をつけなくても育つが、成長に偏りがある子の親はトレーニングを受けた方がお母さんが楽になる、と聞きました。その通りで、3歳の次男が育児楽なのも定型というだけでなく、ペアトレを学んでるのも大きいのかな、と思います。
基本がそこなので多分どこのペアトレもそんなに変わりは無いと思います。
げんちゃんママもコメントの方も皆さん発達育児勉強されていますね。MTパパさん、1日10分でも年間だとそんなに大きいのですね。一緒に頑張ろうと声を掛けて頂いてありがとうございます。
ギャングエイジと言ったのは私ですが、実は意味はうろ覚えでした。そういう時期なんですねー。なるほど…。
私は相変わらず運動ばかりなのですが、運動神経って結局、目だと思うのです。もっと詳しく言うと、目→脳→体という神経の流れをいかにスムーズに、素早く、無駄なくできるか。それには最初に目が、より多く、より正確な情報を、より短時間に脳に送らないといけない。そうしないと脳が判断を誤ってしまう。そこで重要なのが、位置、距離、角度、そういう情報をキャッチできる動体視力です。
動体視力を鍛えるにはげんちゃんも昔やってたお手玉もとてもいいんですが、ギャングエイジの男の子にはちょっと退屈ですよね。私のお勧めは卓球とカルタで間違いないんですが、相手が要るし、手加減もしないといけない。それで最近よくやっているのが、スポンジボールの壁当てです。投げて、跳ね返ってきたのをキャッチして、また投げる。あまり威力もないし、動体視力と反射神経も鍛えられる。部屋でもできますよ。
息子は最近動きがよくなってきて、目、脳、体がかみ合ってきたのを感じます。この調子でいきますよー。
もう一度げんちゃんに、音楽発表会出たいか聞いて下さい。
出たいといったら、練習の必要性を教えてあげ、歌のサポートとして、先生に頼んで、歌を録音してもらい、家で何度も聞かせてあげて下さい。
過去のブログで、ピアノのサポートで、弾いたものを聞かせてあげるというような事かいていましたよね。
歌えるようになれる気がします。
歌えて発表会に参加できたら、達成感も味わえ、自信にもつながる気もします。
結果無理だったという場合も責めず、チャレンジしようとした事自体、褒めてあげてほしいなーとも思います。
頑張って下さい。
いつもながら、何度もすみません。
本人が『やりたい!』と言えた事を褒めて認めてあげて下さい。
やりなさいと言われできた事と、本人がやりたいと言ってできた事は、例え同じ結果になったとしても、本質的に雲泥の差があります。
今回、ソーシャルスキルトレーニングとしては、最高の状況だと思います。
合唱は、みんなの力で成功させるもの、みんなと協力して完成させるもの、みんなの気持ちをあわせるものと、集団生活の中での自分の役割も学べる絶好のチャンスです。
特にいいのは、例え上手に歌えなくても、ある程度歌えて参加できればOKなもので、ハードルが高すぎず、たくさん褒めて上げられる点です。
なんなら、立って参加できるだけでも成長と褒められるので、99%の確立で成功体験となりえます。
それに、発表会(ゴール)があって、みんなと参加し、できた喜びを分かち合える事もいいですね。
今回の事を上手く導く事ができれば、げんちゃんにとって、大きな成長となります。
自分でやりたいと思って頑張れば、成功できるかも、お母さんのサポートも嬉しく感じるだろうし、お母さんが喜んでくれることもとってもうれしいと思います。
別の場面でもいい影響につながると思うし、この成功体験は、げんちゃんの今後の成長の糧となるでしょう。
もし、今回げんちゃんママがやらせない処置をとってしまった場合、結局ぼくはダメなんだ。と劣等感を植え付けてしまい、お母さんに僕の気持ちを伝えても、わかってもらえないと思ってしまうでしょう。
クラスのお友達や先生も発表会の話しをすると思うし、そこに入れず、疎外感も味わうかもしれません。
頑張ってほしいなぁと思ってしまいます。
発達障害の子専用ではありませんが、対応方法の参考になりそうなものを見つけたので、添付しますね。
『子どものやる気を引き出す7つの声かけ法』
http://allabout.co.jp/gm/gc/446258/
お久しぶりです(*^^*)
支援級は先生方との連携プレーですよね
運動会も無事におわり、支援級にしてもらって本人も良かったかなと思います…がやはり学力についてはかなり心配なところはあります
今年は私は厄年かと思うほど想定外のことが起こってばかりで中々子供に全力注げていません
運動会が終わったので先生には学力アップの支援をオーダーしました
今、うちの子の課題は集中力の継続と書くことです
学校でも七田でもこの二点が大きな課題になってます
家で試していけそうな感じなら教材持って学校へのアプローチはやはり必要だと思います
先生方への情報提供もまめに必要だと思います
あくまでも教育のプロであることを忘れずにちょっとづつ私の希望を伝えてます
つくづく素直な先生にあたって良かったと思います
私もげんママさん見習ってまた頑張っていきます
なんか なんの宣言?って感じでスミマセン
度々すみません、こちらのブログを機に、ペアトレの教科書を再度見直していて、記録させてもらっちゃってます。
彼らにとって、世界を理解することが難しく、変化への恐れを感じやすく、決まりきった事を好みます。
もし、彼らのような人々が、大多数で、一般的とされていたら、私たちもその世界で混乱しちゃいますよね?
怒らせるつもりもないのに、怒られたり、自分の考えを言ったつもりなのに、思っていた結果と違っていて困惑したり。
なので、もしよかれと思って環境変化をする場合、勝手にすすめてしまうと、混乱を招きやすいので、きちんと理由を話し、⚪️⚪️日から⚪️⚪️をします。いいですか?と聞いてあげて、了解をとって、事前に変化を教えてあげてからのほうがいいですよ。
みかんママさん
あまりに多忙をきわめていて、コメントがすっかり遅れてすみませんでした。
細かく色々書いて下さりほんとにありがとうございます。
こどものもっていきかたとして、私もふくめて読んでおられる方に大変参考になりますね。
今回の件は、げんちゃんを、参加させなかったのは、げんちゃんが、本心で、まったく参加したいと思ってないことがわかっていたからなのです。つまり、苦痛です・・・・
いやだ、と言ったのは、参加しなければいけないのかな~。まずいことになるのかな・・・という、刑罰的な物を、自分が感じ取っていたの田と思います。私は、ほんとにどっちでもいいよ、と思って聞いたのに、刑罰的な方にとったようです。
その証拠に、家でリラックスした時に、
「あの、歌は、すごくいやだ。やりたくない。音楽はきらいだ。」
とほんとにいやそうに言っていました。
「天使にラブソング」の映画みたいなすぐれた曲、すぐれた指導者のもと・・・というのではなく、ほんとに、苦痛そのものの授業でした。
無理にこんなのに、参加させてたら、普通の子でも、音楽嫌いができそうです。
私の文章がつたなくて、つたえられなかったので申し訳ないです。それと、もう、発表会が、1週間くらい前になってるのも、理由です。
げんちゃんは、みんなで達成感を味わうために、みんなで努力することがまったくできないステージでもないです。
サッカーでも、ピアノでも、目標を決めて、あきらめずに、達成して言ってる物も大分出てきました。能力はあがってきてるようです。ただ、自分が納得しないものに、つきあって、努力する・・・という、高度なわざは、まだありません。それを、無理させれば、逆に達成感どころか、その課題が大嫌いになってしまうかな~、と思ってます。
今回は、それかな~・・・
でも、みかんママさんの、細かいアドバイス、とても参考になります。具体的に書いてあるので、教科書のようですね。
また、次回、げんちゃんが、取り組んでもいいな、と思える課題で、がんばらせる時にとても役にたちますね。
ありがとうございます。
fukanさん
ほんとにそうですね~。
学校の授業をたまに見に行きますが、芸術の科目や体育は、素人の先生が教えているので、あ~これなら、出なくてもいいか~。自前で、本職におけいこごととして師事させていれば十分だ・・・というのが多いです。
最初は、そうとはわからずに、音楽や図工の時間を休んでホームスクールは?なんて思ってましたが、見学をして、
「あ~、出なくてもいいか~。」(笑)と思いました。
習字も知り合いのプロのおばあちゃんのとこにたまに遊びに行って、てほどきをうけさせてみたりしてます。最初の基礎を、しっかり本職におそわることはとても大事ですよ。
学校に習ったばっかりに、嫌いになっちゃった、という教科は案外普通の子でも多いですよね。
fukanさんも、運動のトレーナーをつけられたのは、ちょっとお金はかかるけど、ほんとによいことですよね~。
こちらでは、発達ママのママ友が何人かいて、みんな、ばりばり取り組んでおられて、はげまされます。たまに、いっしょにごはんします。なかなか時間がとれないのがたまに傷です。子どもが普通の子だったら、ありえない、忙しいスケジュールになってるママばかりですが、とても素敵な方です。戦友みたいです。しかし、遠いですね~。九州からは。(笑)
fukanさん
ペアトレ、みかんママさんといい、色々あるのですね。でも、療育でやってくれるのってこっちはないです。私は、まずそこからだろう・・って思うのですが、各論をちょろちょろやってるだけ、という感じですよ。どこにあたるかで、その子の運命がかわるかもしれないなんて、ちょっと怖いですよね。よい出会いをしながら、素敵な子ども達に育ったほしい物ですね。
MTパパさん
すごく目のこと、大事だとあらためて思いました。それで、さっそく、スポンジボールの羽子板みたいなゲームを買って、ちょくちょくやるようになりました。最初は下手だったのに、やるほどけっこううまくなっていって、本人も、とても楽しい様子です。勉強の合間にやると、何より、復活が早いのは、たぶん、目をしっかり動かすし、体も動かすからだと思います。体の細かい動きも必要とします。
昨日、隣の2年生のかしこいぼうやと、遊んでいて、その遊びをやってました。げんちゃんの方がうまかったです。そもそも、1~2年だと、まだラケットを使って打つようなものは、そこまで発達してないのかもしれないですね。げんちゃんは、自分の方ができるとわかって、なんか、余裕がありました。とにかく、能力が上がれば、ソーシャルにも、余裕が生まれるんだな、と思いました。
でも、目の機能が、10歳までというのは、がんばらなくちゃ、と思えるコメントでした。ありがとうございました。
junママさん
ソーシャルのよい教室に通えてほんとによかったですね。ほんと、親は、ほめることが、他人より、消極的になっちゃいます。
それが、積もり積もって、コンプレックスを作ってしまったりしますから、他人にかかわってもらうのはいいですよね。
ぼうやも、すごく進化してますね。アスペルガー的な要素は、げんちゃんとは、また別の苦労がありますよね。お勉強は、けっこうできるのに、なぜ、ソーシャルだけ、何かが足りない・・・的なのって、ほんとになぜなんでしょう。脳のどこをどう、開発すればいいのだろうか・・・
もう知りたくてたまらない部分です。
まあ、げんちゃんは、お勉強も、いっぱいいっぱいのばして今の程度なので、やることがいっぱいありすぎます~。(泣)
ところで、合唱の時間って、私も、すごく退屈だったことがあります。やっぱり嫌いな曲でした。嫌いな曲をやることほど、憂鬱なことはないですね~。好きでも嫌いでもない曲でもけっこう苦痛なのに・・・
げんちゃんは、
「あの曲は、古いからいやだ。」
というのは、言い得て妙です。妖怪ウオッチのような曲で育ってる子たちに、直立不動で歌わないといけないような、リズム感のない、抑揚のない曲を与えても、なかなか乗れないですよね~。子どもさんも、うちの子も、そのあたり、正直なんですよね。
あきさん
よくわかります。
自分のコンディションが悪いときほど、発達育児がつらい時ってありません。でも、子どもって、そういうのおかまいなしなので、大きくなったら色々非難したりしますよね~。親だって、生身だし、そういう中で、おまえをがんばって育てたんだよ・・・って言ってやりたいことって、世の中いっぱいあるんでしょうね。
子は、親が、完璧な環境を準備するのがあたりまえ・・・みたいなスタンスですからね~。
そう言うことも含めて、色んな他人の苦労がわかる大人に成長してほしいですね。この子たち。
でも、がんばっていきましょう。
支援の先生も、つまるところ、親の気持ちまでは理解できません。コミュニケーションをとって、どういう風に自分は、分析していて、それに対して、こういう目標をたてていて、現状の小さい目標はこれ。だから、今学校ではこういう方向でやってほしい。と細かいとこはまかせつつも、お願いするのがよいですよね。
どんな先生にあたるかも大きいです。祈るしかないですね~。
オモチャのラケットでラリー、十分だと思います!賢い子より何かが上手にできるって素晴らしいですよね。もし私が見てたらニヤニヤしちゃいます。
ラケットの動き、小1くらいでも全然伸びます。今の子って野球やらないので、器具を介してボールを操作することに慣れてないんですよね。だから運動してる筈の子でも、習ってるのが水泳とサッカー、とかだとラケット系の当てるコツや力加減はさっぱり分からないです。
サッカーは運動量、ルールの簡単さ、用具の少なさ等々、子供がやるには野球よりよっぽどいいスポーツなんですが、動体視力はあまり鍛えられない気がします。
そして、やってるうちに普通に上手くなってくる、こういうところにゴールデンエイジの萌芽を感じませんか。うちの息子も、やってみろ、と言ったらできたことが増えてきた気がします。
微妙な力加減の調節にもなるので、気晴らしにラケット系のスポーツを取り入れるのは良いことだと思います。
動体視力なんですが、成長の臨界期が10歳前後というだけでその後も成長しますよ。遠視力と違ってかなり長い間衰えずに維持できるそうです。ただ、大人になってから動体視力の良い人と悪い人に同じ訓練を施しても、それぞれ伸びますが決して悪い人が良い人を逆転することはないそうです。
運動神経は目で決まる、という私の推論とあわせて、やはり子供の時運動神経の悪かった人が大人になってから努力しても逆転することは出来ない、というのが実際のところかな、と思います。
そういう人は、大人になってからも発達する筋力や持久力で巻き返す感じでしょうか。
話は変わりますが、ドラえもんの宇宙開拓史って映画ご存知ですか。劣等生ののび太が別の星ではヒーローになれる。子供なら誰でも一度は夢見る設定ですが、げんちゃんが今味わってるのはそういう世界なんだなぁ、と思いました。誰だって自分がヒーローの星に住みたいですもんね。
人の評価は相対的だから先生も通級と普通級で評価が変わるし、げんちゃんも揺らぐと思います。げんままさんが優等生のげんちゃんと劣等生のげんちゃんをつなぐ不動の評価軸になれたらいいのかなぁ、なんて思いました。長々とまとまらない話を失礼しました。
MTパパさん
なるほど~。すごい分析ですね~。確かに、小さな100均のラケット使って、やっていくごとにうまくなっています。もし、去年だったら、あ、だめだね。まだそこまで行ってないか~。という感じだったと思います。うまくなるべく基礎が育ったのでしょうね。
サッカーに水泳、まさに、げんちゃんがやってるのはそれだけ、まあ、自転車を加えるくらいです。
このスポンジボールのラケットでの打ち合いは、かなり手応えがあります。何かが伸びるんだろうな、という。目と、からだ、それですね~。
それから、のび太君がヒーロー・・・言い得て妙です。支援クラスは、げんちゃんのために、まだとりあげてはいけない物なのだと思います。親としては、普通クラスで、みんなについていってほしいと思うけど。
先生も、
「普通クラスでも、やれるんでしょうけど、やっぱり、本人がきついかな~。」ともらしておられました。
それは、普通クラスでは、かなり、本人の負担が大きいということでしょうね。ついていってるように見えても、どんどん、げんちゃんを追い込むようなとこもある思います。今の形は、げんちゃんにとっても、ハッピーなのでしょう。その中で、自分で大切なことを感じ取って、ステップアップしてほしいです。
ありがとうございます。
ほんと、いつもながら、皆さんの洞察力や努力がすごく勉強になります。ありがとうございます。
げんママさんの勉強会、開催されるなら是非参加したいな〜。私は遠方ですけど、身近に頑張っている発達ママが少なくて(受け入れて諦めてる?方が多い)、頑張り屋さんのママさんに会いたいな〜と思います。
ところで、コメント欄でお借りしてしまってすみません。
MTパパさんに質問です。
運動神経が目で決まる、というのすごく興味深いです。うちの息子(小2:ADHDです)は眼球運動が弱くて平衡感覚に問題があるだろうなあという子です。ビジョントレーニングでかなり文字は読めるようになり、最近は児童書一冊一日で読んだりしますが、読み間違いが多いです。
また、平衡感覚弱くて片足立ちが長くできない、球技苦手、身体をグルグル回しても目が回らない、など何か目に問題あるだろうなあと思います。
普段家で取り組んでいる運動は、トランポリン(3分くらい)体幹を作る簡単な体操、水泳(週3〜4回、1kmくらい泳ぎます)です。ですが、中々亀の歩み、という感じです。
水泳は選手育成コースで試合にも出るようになってきたのですが、周りは健常の運動神経の良い子が多いのか?育成クラスでもビリ、試合でも下から数えた方が早いです。。
私はかなりの負けず嫌いで、すごく影で努力するタイプだったのですが、息子はのんびりしてて、ビリでもあんまり気にしないという^^;;;; 私はなんとかしてビリから脱出させてやりたいですが。
思うに、身体がまだうまく使えていないような感じもします。
(肩を使って手をあげる、と頭で分かってても水中でできない)
何か息子がもっとよくなるために出来ることないかな〜と思うんですが、健常の子とは違うアプローチが必要なのかなあと思ったりします。
げんママさん、続けてすみません><
ところで、私は地元の発達の気になる子の親同士の集まり、のようなものに時々参加しているのですが、そこで感じる違和感があります。
なんというか、「改善する」とかの言葉が暗黙にNGワードとされてる感じがあるんですよね。
「治る」というのは確かに極端だと思うのですが、「親が頑張る、なんておかしい。子供も親も十分がんばっている」と。。。
お子さんの障害を受け入れているところに、治るとか改善するとか努力をもっとする、とか言われたくないって言うんですが、私にはその心理が分かりません。。。
私は息子がほんの少しでもよくなるのであれば、全て試してやりたい、この子の一生を左右するのにっていう考えなので。
どうして諦める?んだろうってすごく不思議です。
Rさん
コメントありがとうございます。2歳で、自閉症スペクトラム傾向・・・とわかったんですね。ショックでしたね。気持ちわかります。私も、しばらくどうしていいのかわからなかったです。でも、2歳でわかったのは、ほんとによかったですね。2歳といえば、まだ成長のスタート時点。ママのがんばりでどういう風にもなれると信じます。それに、前向きに、何でもしたい、というママは、多数派ではないです。笛ふけど踊らず、という人をたくさん見てきましたから。
さて、食べ物ですが、げんちゃんも、牛乳と卵の遅延性のアレルギーがあったので、(アメリカに血液送りました。)小学校に上がる頃は、厳密に除去してみました。でも、あまり、結果を感じなくて、今は、あまり気遣ってません。とりあえず、徹底してやってみて、効果を判断して、そんなに違いがないのであれば、食生活が不便になる食事制限は、できるだけ、とらない、程度でよいのではないか、と思います。
げんちゃんも、にこにこして、あつかいやすいおとなしい子でした。それで、見つけられませんでした。でも、2歳で見つけてもらったのというのは、げんちゃんより、ずっと未来が進化してる、ということだと思います。
つらいこともたくさんあるけど、前向きにやっていったら、楽しいことが、今までより、たくさん増えます。がんばりましょうね~。何か先輩として、お役にたてればうれしいです。これからもよろしくお願いします。
Rママさん
目のことほんとに、タイムリーですよね。MTパパさんありがとう。
コメント読んでて、思いました。運動能力って、いくつかの流れがあって、まず、体をささえる体幹、筋力・・・それと、スキルに属するもの。この二つに私の中で分けられてます。もしかしたら、もっと分けられるかも。
げんちゃんは、最初、そもそもの筋力がないというとこにアプローチしました。がっちりなってきて、ボール運動とか、細かいスキルに移りました。
粗大運動から、微細運動・・・これとは意味違うかもしれないけど。そんなかんじかな~。私も、感覚的にやってますが、言葉にできるほどわかってないかもですね~。
微細運動になってくると、確かに、目と手の強調とか、リズムがわかる、とか、より高度な部分が必要になってきてますね。
もっと、このあたりを、細かく分析できるチャートがあるといいですね。
それから、障害を受け入れている・・・これよくわかります。支援クラスで交流するまでは、エジソンママとかの交流が主体だったので、みんな前向き、自分と同じ、という感じだったので、学校の支援クラスのママたちが、皆そういうわけではなかったので、ほんとに驚きました。
ここで交流していただいているママパパは、ある意味、少数派なのだな~と思います。ブログがあってこそさがせるママ友でしょうか。これからもよろしくです。
本当、どこにあたるか、誰と出会うかで人生左右されやすい子達ですよね。誰でもかもしれないけど、どん底にいく振り幅が人より大きいと思います。息子は過去の習い事には外れでしたが、保育園学校の担任には恵まれてきました。特に二年生になってからの担任はとても良い先生で、息子を理解してくれています。息子の限界を受け入れるやり方でした。一見甘やかしてる様ですが、限界を受け入れる事により、息子はわかってくれる人がいる、と安心し、限界を自分の言葉で伝えられる様になりました。自分の言葉で伝えた事を褒めて下さり、それによって発言する事を怖がらなくなるようになり、今ある事に興味を持てるようになったら頑張る事を覚えました。二学期からの学校行事の練習もだいぶ参加する様になり、ギリギリですが勉強も〔漢字以外〕何とかついていってます。けど、これは息子に合う指導をしてくれる担任ありきてす。息子は特に拒否反応がとても強いので納得行かなければ勉強もしないだろうし、学校も行かなくなると思います。理解ある担任が珍しいだけで、学校も医者も大半は発達障害を理解していませんよね。せめて興味を持って理解しようとする先生が増えて欲しいなと思います。
そしてげんちゃんママ九州でしたか‥‥
遠い、遠すぎでしたね、、笑
残念です。私の友達でも我が子を受け入れて一生懸命育児をしてる素敵なママいます。
価値観が同じで子供の悩みも同じで、特徴は違えど、根本的な悩みは理解しあえる大事な友達です。
げんちゃんママとこうした機会で知り合えたのも何かの縁だと思ってます。
これからもブログのコメントを通してよろしくお願いします。
Rママさん
水泳スクールの選手育成コースとは、凄いですね。うちの息子はスクールに五年通ってやっと8mですから、私ごときがアドバイスできるようなこともありませんが、私の知っている範囲で申し上げますね。
運動神経がいい人の定義は色々あると思うんですが、私の考えではただ単に足が速いとか力が強い人ではなく、どんな動きも素早く身に付け、スマートにこなすことができる、そういう人をイメージしています。実は水泳のトップ選手でも水泳ばかりやっていた人だと反復横跳びが全く苦手だったり、立ち幅跳びの跳びかたがわからなかったりする人もいるそうです。
個人的には、水泳は私の考える運動神経の良し悪しはあまり関係ないのかな、と思います。
水泳のレベルアップに必要な持久力の成長の臨界期は中学生以降に、筋力の成長の臨界期は高校生以降に来ますので、基本的な体力づくり以上の向上を求めてトレーニングしても今はまだ効果は薄いと思います。
小学校低学年のうちは水泳やかけっこなどの粗大運動メインのスポーツは、もって生まれた能力の優劣で勝敗が決まってしまうのかな、と思います。ゴールデンエイジの伸びで生じる差も、結局顕在化してくるのは高校生以降になってからですし、今はまだ逆転は難しいかもしれません。
お役に立てるとすれば、体の動かし方の不器用さの改善についてです。うちの息子もそうでしたが、体の動かし方の不器用な子は肩甲骨周りが上手くまわらないようですね。クロールなどでは腕の動きのぎこちなさに直結してくると思います。
目と水泳が関係してくるとすれば、コーチのお手本を見て、その通りに動きを真似することです。コーチの動きを正確に見定められないとおかしな動きになってしまうのかな、と。ですが動きの不器用さの大きな原因はボディイメージの歪みだと思います。自分のイメージではこう動いてるはず、でも実際は全然違う動きをしてる、というやつです。
MTパパさん、ありがとうございます!!
いきなりのリクエストにも関わらず、丁寧にコメントいただけて感謝ですm(_ _)m
げんままさん、コメント欄使わせてもらってありがとうございます。
素晴らしい分析ですね。持久力と筋力の臨界期は知りませんでした。そんなのがあるのですね!
同じ育成で泳いでる子を見ても、コーチの説明を聞いてすぐにこなせる子と、こなせない子がいます(もちろん息子もこっち)この辺りなんでしょうね。水の抵抗や姿勢など、考えて身体を動かせて泳げるようになるまでは気長に応援する、てことですよね。
実は夫とその弟が水泳選手でしたが、片方は小学生時代はたいしたことなく中学から徐々に強くなり、片方は小学生時代は表彰台にいたのに中学から落ちていき辞めたそうです。
今できることといえば、持久力をつけるというか、疲れに慣れさせるための体力作りでしょうか。いつも試合の50mレースで後半バテバテの泳ぎになってしまいます^^;
練習中にグルグル何周も泳ぐ時も他の子よりすぐにバテてるので。キックの練習だと遅くなるから脚力が弱いんでしょうね。
先は長いけど、好きみたいだし、なんとかしてやりたいですね^^;
それに特性のせいか、練習中にふざけたり真面目にしてないことも一因なんでしょうね。(>_<) ほんとまだまだ子供で、泳ぎ待ちの時は水遊びしてるという幼稚さです。。。
改善方法としては、息子さんの動きを逐一ビデオ撮影し、その場で本人に見せる。「ほら、お前今こんな動きしてるんだよ」と。そして動きを修正し、また撮影して見せる。こうしていくことでボディイメージと実際の動きとのズレがだんだん改善されていくと思います。鏡張りの部屋で自分を見ながらダンスや武道の演武をするのもとてもいいですが、なかなかそういう場所もないと思いますので、ビデオを利用するのがいいかな、と。うちの息子の柔道もそれでずいぶん改善しました。
素人考えで恐縮ですが、今思いつくのはこの程度でしょうか。息子さんの運動量は充分だと思いますので、体力系トレーニングはこれ以上要らないと思います。
MTパパさん、投稿がかぶっちゃってすみません。
そして、すごい!!!!
肩甲骨、ボディイメージ、まさにそれです!!
クロールも背泳ぎも肩甲骨から肩のローリングを使って肩から腕を動かすようにするのですが、息子はこれがうまくありません。クロールで腕が上がりきらず回してしまうことがあり、失速の原因になっています。背泳ぎでは腕が真上まで回らなくなってしまったり。同様にうまく腕が回せずバタフライもうまくいかない。平泳ぎが一番すき(肩がラクなのかも)だそうです。
ボディイメージについては、ビジョントレーニングの一貫で少しはやっていたのですが、苦手としている眼球運動の方ばかりやっていたので、あまりやっていませんでした。
水泳以外の運動の苦手さは、ボディイメージの歪みによるもののように思います。
すごいヒントがいただけて、感謝×100です!
本当にありがとうございます!!
すみません、ガラケーから仕事の合間に打っているので遅くなってます…
旦那様が水泳の選手だったんですか!凄いですね!
サッカーや野球でも、小学生の時に全国大会の常連だった子が中学高校で伸び悩み、新しい子が台頭してくるのは珍しい話ではありません。違いは、そのスポーツしかやらなかったか、他のスポーツ(かそれに類するトレーニング)もやっていたかどうか、だそうです。一つのスポーツに打ち込むのは日本人の美徳的には美しいようですが、発達する神経が偏ってしまうので伸びしろが少なく、成長してから伸び悩む原因となるようです。脳の可塑性の高い少年時代にできるだけ多くの動きを経験させることがその後に活きてきます。
長々と失礼しました。あくまで素人の意見ですのでご参考までに…
頑張ってください!
すみません、付け足しです。
腕の回し方も息子さん本人はちゃんとやれていると感じているのかもしれませんので、泳いでいるところをビデオ撮影して、見せてあげるのがベストだと思います。そして肩甲骨周りのボディイメージを改善していくのです。
他のスポーツについてはボディイメージ+動体視力が足りないのかな、と思います。読書は平面上での視点の移動ですが、球技は距離を測る深視力も関係する三次元、ボールのスピードも加味すれば四次元の視力が必要です。こちらは水泳ではなかなか鍛えられない分野ですので、フォローしてあげたらいいのではないかと思います。
長々と失礼しました。息子さんの成功を期待しています。
MTパパさん
アドバイスありがとうございます!
MTパパさんの運動への知識、観察眼には本当に敬服します。素晴らしいですね。是非、もっともっと発信してほしいくらいです^^
ビデオ撮影ですね。個人的に練習行ってるプールでは撮影禁止ですが、普段のスクールでの練習は撮影OKなので、撮ってみて見せてみます。
実は、同じ育成クラスの一人の男子が、執拗に息子をイジメてくるんですよね。ビリでタイムが遅いことを、あからさまにバカにします。息子も幸いにも落ち込むことはなく「あいつより速くなりたい!」と言っていますが、体力や潜在能力で今は勝てません。
でもいじめるその子も、ギリギリでリレーに選ばれるかどうか、くらいで、もっと速い子はいっぱいいます。なぜ息子をいじめるのか?理由がわかりません。
息子が注意力散漫で先生に注意されること多いからか、「バカにしてもいいやつ」と思っている感じがします。
あまりにヒドイので担当コーチからも注意をしてもらいましたが、担当コーチは優しいからか効果なく、引き続きイジメてくるそうです。「○○はアホだ」「○○は一番遅い」とか、歌を作って泳ぎの待ち時間で言ったりなど、好き放題です(閲覧席から見ててもよく分かります。息子より私が腹立ってるかも)
もう少し権限のあるちょっと厳しめのコーチに知り合いがいるので相談すべきかどうか、今迷っています。。
夫によると選手育成では言葉の暴力やイジメもよくあるそうですし><
気づいたら、かなり脱線してしまってすみません><
という訳で、息子を応援してやりたい!と思っています。
まずは試行錯誤しながらも親子で一緒にがんばる!息子も今回のような体験があって成長になることでしょうし。
ほんとうに、ありがとうございます!!
Rママさん、辛い思いしましたね。けど、気持ち落ち込まずもっと早く泳ぎたい、と頑張れる息子さん羨ましい。素晴らしいです。
うちは、こないだ兄弟喧嘩というか、次男が悪くて次男を怒っていたらなぜか長男が傷ついた顔。理由を聞けば、次男が悪さした事に悲しみと怒りと、同時に次男を悪く思う自分に辛くなったらしいです。
次男は泣くし、長男は傷つくしで私ががっくり。息子の気持ちをよく聞き何とか落ち着きました。つい、私がうるさい、と言うと傷つくし、うるさい、も言えません。とは言えいってしまうんですけどね。言った後に謝り、息子もなぜ今待てなかったのかを話し合い、こんな感じつです。いつも。
話しそれて愚痴みたいになって申し訳ありません。
うちも何とか水泳教室始められたので、スポーツで身心ともに鍛えられるといいです。
Rママさん
素人の考えですので、きっと専門の方が見たらおかしなことも沢山言っていると思います。本当に話し半分でお願いします。
息子さんを苛めている子がそこまで速くないのは分かります。前にも書きましたが、勉強にしろ運動にしろ凄くできる子はそれに対してコンプレックスがないので出来ない子なんて気にしません。自分にも出来ない不安があるからこそ、もっと下を見付けて、安心するのです。そして周りにもこいつは俺よりも下だ、とアピールするのです。うちの息子にもそんな相手がいます。何人かは実力で黙らせましたがまだいます。いつかは見返してやりたいですよね。その日までお互いに頑張りましょう。